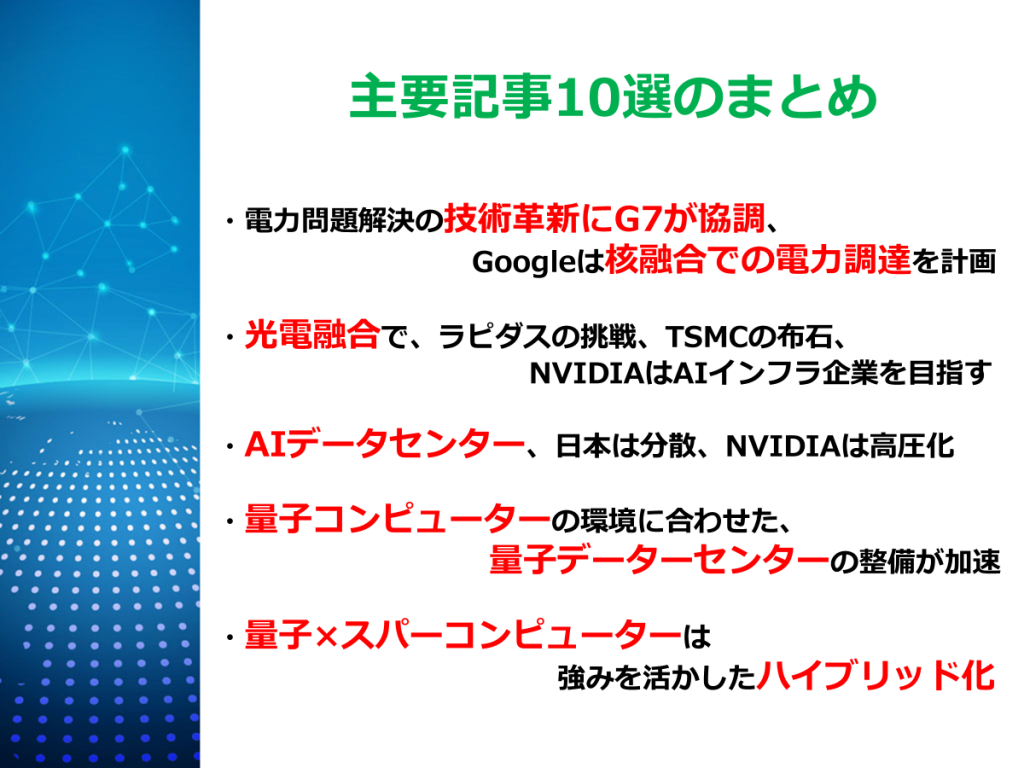【sevensixTV】に第137弾の動画を配信しました。
00:39 G7が電力問題に国際協調で対応へ
01:24 Googleが核融合で電力確保へ
02:14 光電融合で省エネ革命? 日本は素材強みも製造で出遅れ
03:11 TSMCが1.4nm+光電融合技術を発表
03:58 NVIDIAが「AIインフラ企業」宣言
05:26 ソフトバンク×KDDIが旧シャープ工場跡に分散型AIデータセンター構想
06:26 NVIDIAが提唱する800V HVDC構想
07:21 量子コンピューター専用データセンターの整備が進む
08:09 富士通「富岳NEXT」でAI向けスパコンへ
09:05 IBM × 理研が量子・古典ハイブリッド計算へ
09:49 今月のまとめと雑感(コンビニがデータセンター⁉︎)
今月は電力関連の国際的な動向、光電融合をめぐる国内外企業の動き、そしてAIデータセンターと量子データセンターの潮流、最後に何かと比較されるスーパーコンピューターと量子コンピューターの動きについてお届けします。 直接的にデータセンターと関連していなさそうな記事も、データセンターとの関連を中心にまとめておりますので、最後までご覧いただけますと幸いです。
【おすすめ関連動画】
▶ 第1弾:AI革命!データセンターの役割とその進化│Vol.118
▶ 世界のデータセンター市場動向から、国内(政府・民間企業)動向を考えてみる│Vol.119
▶ 生成AI/データセンターシリーズ:光技術がもたらすパラダイムシフトの全貌に迫る!│Vol.120
00:39 G7が電力問題に国際協調で対応へ
1つ目は電力関連から、技術革新への国際協調の動きを見ていきたいと思います。
最近、G7がAIの急速な普及に伴う電力消費の増加に危機感を示し、技術革新による対応を協調して進める方向で動いています。特に注目すべきは、AIの心臓部とも言えるデータセンターの膨大な電力消費です。G7は、各国で電力使用量や予測データを共有し、効率的なエネルギー運用に繋げる仕組みを検討しています。
国際エネルギー機関の試算では、2030年までに世界のデータセンターの電力需要は2倍以上に達するとされており、約半分は米国が占める見込みです。G7は、AIモデルの省エネ化やデータセンターの最適化に向けた具体策を成果文書に盛り込み、秋に予定されているエネルギー関連会合に向けて議論を加速しています。
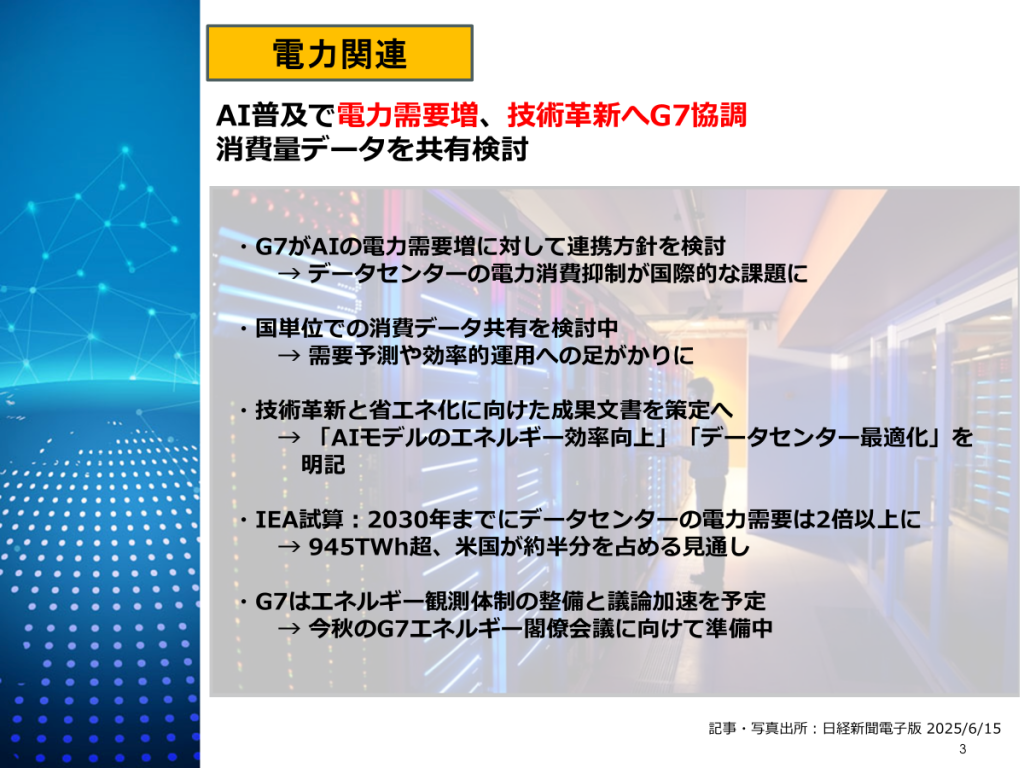
01:24 Googleが核融合で電力確保へ
続いて同じく電力関連ですが、Googleの最新の電力調達戦略についてお届けします。
AIの急速な普及により、データセンターの電力消費は今後さらに増加すると先ほどの記事でもお伝えしましたが、そんな中、Googleは次世代技術からの電力調達に先行して取り組む模様です。Googleは米国の核融合ベンチャー「コモンウェルス・フュージョン・システムズ」と提携し、2030年代前半に核融合発電による電力を導入する契約を発表しました。
核融合は、海水由来の重水素を燃料とし、CO₂を排出しない“夢のエネルギー”とされており、今後のクリーンなデータセンター運営に欠かせない技術として注目されています。
GoogleはAIと脱炭素化の両立を目指し、将来の安定電源として核融合を選んだ形です。他にもSMR(小型原子炉)など複数の電源を確保する動きも見せており、電力確保がデータセンター戦略のカギを握る時代が本格化しています。
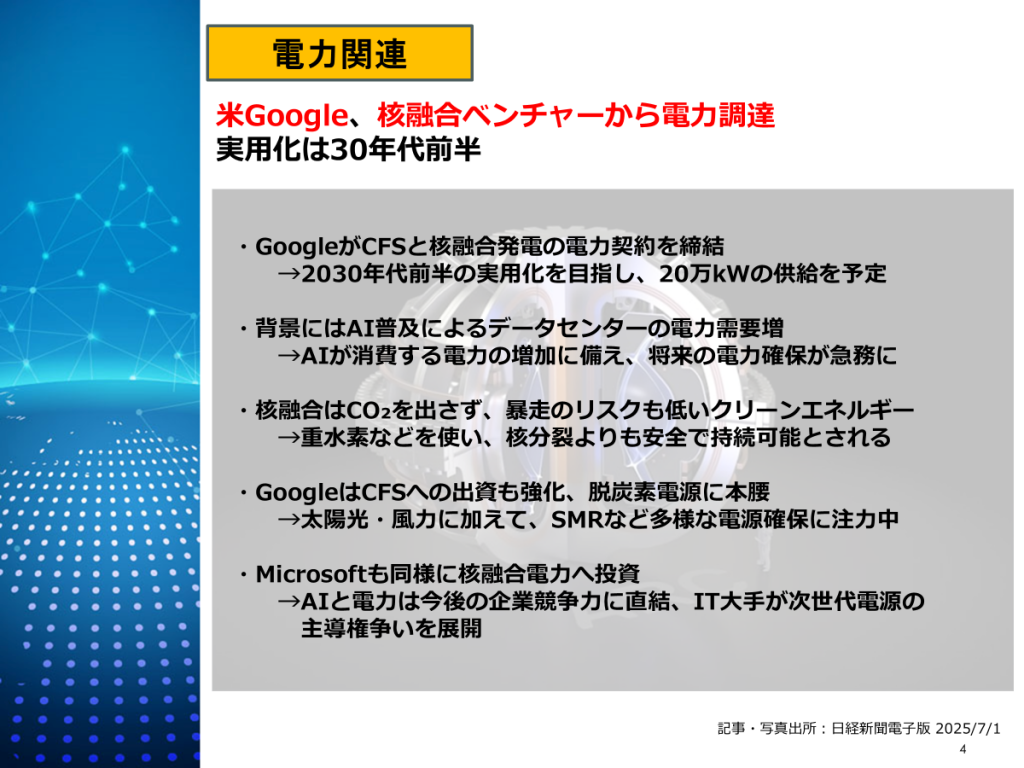
02:14 光電融合で省エネ革命? 日本は素材強みも製造で出遅れ
つづいては、そんな電力問題の解決策として注目されている光電融合技術から、まずは世界における日本の立ち位置を確認していきたいと思います。
ここ数年、データセンターの電力消費は爆発的に増えていて、その主な要因の一つが生成AIの学習処理です。そんな中、注目されているのが「光電融合」技術です。これは電気信号による伝送を光に置き換えることで、通信の高速化と省エネを同時に実現できるというものです。特に「CPO(コ・パッケージド・オプティクス)」という技術が最先端で、NVIDIAやブロードコムが開発を急いでいます。
データセンターではこのCPOを使うと、通信ポート1つあたりの消費電力を最大3分の1に削減できる可能性があります。ただし、現状でこの技術を量産できるのはTSMCなど海外勢に限られており、日本は素材では強いものの、最終製品の製造では遅れをとっています。そんななか、今、ラピダスがそのギャップを埋める存在として注目されており、2027年の量産開始が期待されています。
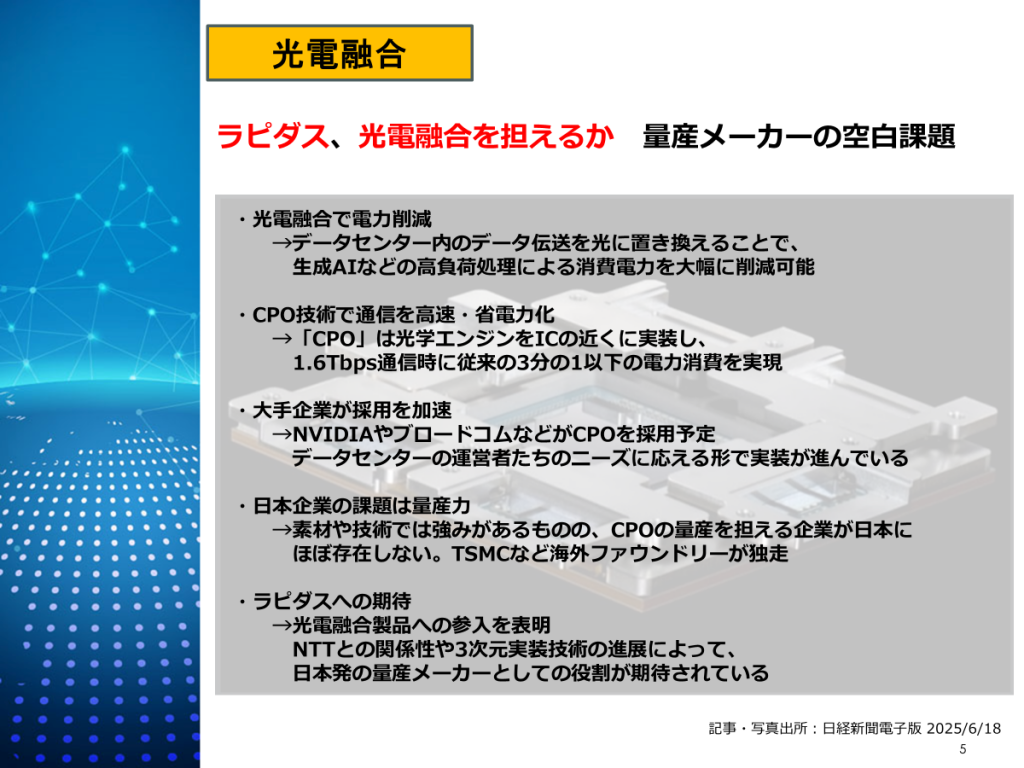
03:11 TSMCが1.4nm+光電融合技術を発表
続いて光電融合の主要プレーヤーであるTSMCが発表した、1.4ナノ世代の半導体開発と光電融合技術に関するニュースをご紹介します。
TSMCは2028年に1.4nmの量産を開始予定で、AIチップ向けの演算性能を飛躍的に高めます。特に注目なのが、データセンターの省電力化に直結する「光電融合」技術です。これは、プロセッサーと光電変換回路を1つのパッケージに集積し、電気ではなく光でデータを伝送する仕組みです。
従来のプラガブル方式と比べて伝送遅延は90%以上削減され、消費電力も10分の1以下に抑えられる見通しです。NVIDIAやBroadcomもこの技術を採用しており、2025年には実製品が登場予定です。AIとデータ量が爆発的に増える時代において、データセンターの省エネ対策として非常に注目される技術です。
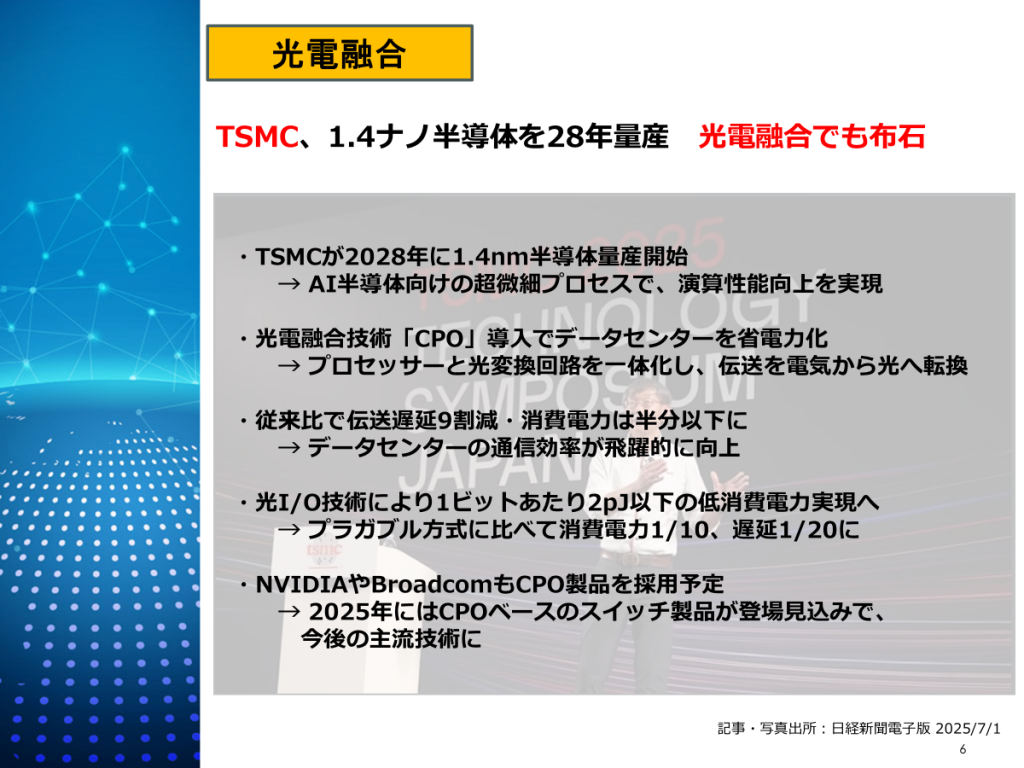
03:58 NVIDIAが「AIインフラ企業」宣言
光電融合最後の記事はついに時価総額4兆ドルを突破したNVIDIAの、次なる成長戦略についてご紹介します。
AI半導体で絶対的なポジションを築いたNVIDIAですが、今、単なる「半導体企業」から「AIインフラ企業」へと進化を遂げつつあります。ファンCEOは「我々は社会に欠かせないインフラを提供している」と語り、電気や水道と同じレベルの存在感を目指しています。
注目すべきは、台湾の大手メーカーとの連携です。TSMCや鴻海(ホンハイ)と組み、AIスパコン拠点や100MW級のAIデータセンターを台湾に複数構築中です。BlackwellアーキテクチャーのGPUを核に、AIモデルの開発から製造現場までをつなぐ“AI Factory”の構想を推進しています。
さらに、NVLink Fusion(エヌ・ブイ・リンク・フュージョ)という新技術で、NVIDIA製GPUと他社製CPU、AIアクセラレーターの接続を柔軟にしています。これにより、ハイパースケーラーや企業が自由にAI基盤をカスタマイズできるようになります。
また、量子コンピューティング分野でも台湾や日本との連携を強化しており、富士通やQuEra(クエラ)と協業し、量子研究拠点に参画しています。さらには量子+AIという未来の計算インフラにも投資を拡大しています。
NVIDIAは今後、光電融合やロボット、量子コンピューターといった新分野にも踏み出すことで、AIインフラ企業としての地位を一層確かなものにしようとしています。
データセンターの視点から見ると、NVIDIAは今や世界のAI計算基盤の中枢です。今後の成長が、業界全体のインフラにどう影響していくのか、引き続き注目です!
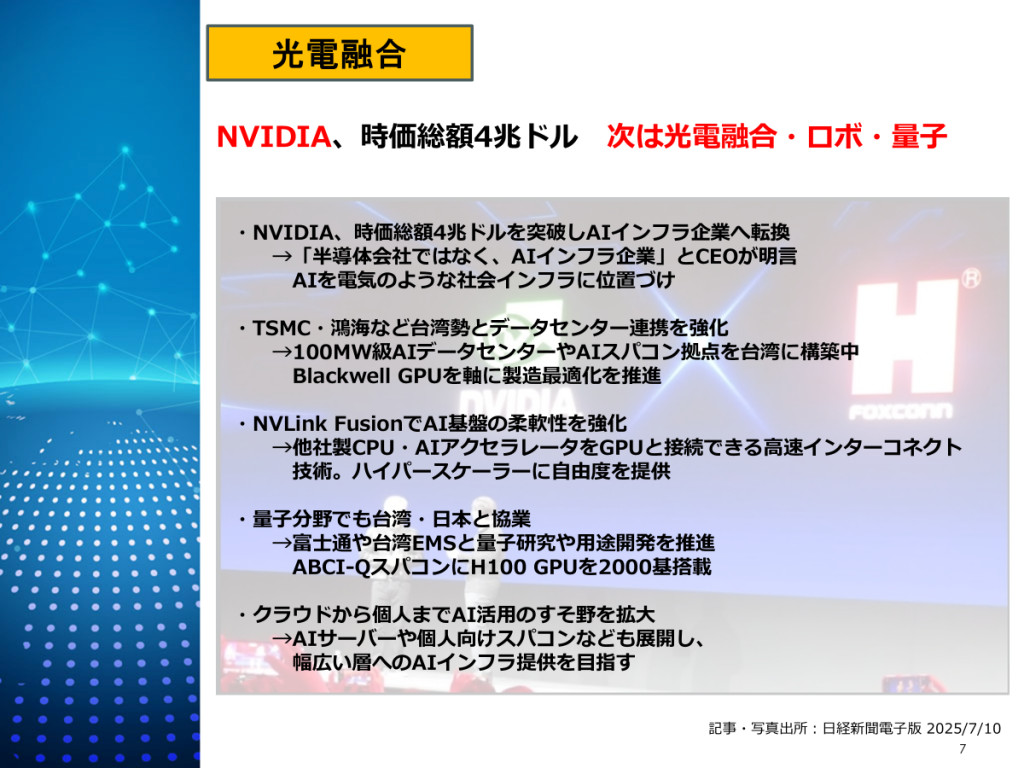
05:26 ソフトバンク×KDDIが旧シャープ工場跡に分散型AIデータセンター構想
続いては、AIデータセンター関連の、国内動向をご紹介します。
いま、ソフトバンクとKDDIが、関西の堺市にあるシャープの旧工場跡地を活用して、AI対応の大規模データセンターを建設しています。
特に注目すべきは、これが単なる都市集中型ではなく、全国に分散配置する超分散型データセンター構想の一環だという点です。
具体的には、高負荷処理が必要なAIモデルの学習などは大規模データセンターで、反対に、負荷がさほどかからない一般企業での日常的な推論処理は地方の小型データセンターでと、このように用途に応じてデータ処理を最適化する次世代インフラを目指しています。
これは外資主導だった日本のクラウド・AI基盤を、国産の計算インフラへと転換する大きな一歩です。
さらにソフトバンクは、苫小牧やその他の地方にも同規模のデータセンターとを展開予定で、KDDIはローソンの店舗をミニデータセンターとして活用する構想を進めています。
まさに、データセンターが全国に広がり、地方から日本のAI社会を支える時代が始まっています。
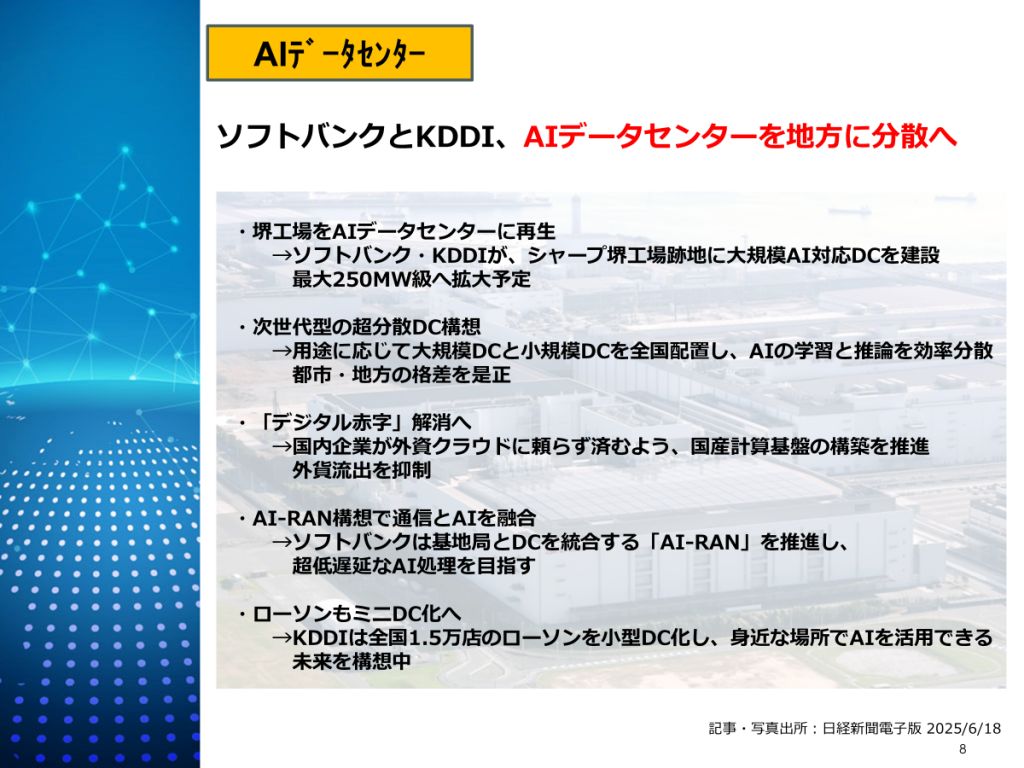
06:26 NVIDIAが提唱する800V HVDC構想
AIデータセンター関連、つづいてはNVIDIAの動きについてご紹介します。
AI時代の急激な電力需要の増大に対応するため、NVIDIAがAIデータセンター向けにHVDC(直流800V給電)構想を打ち出しました。これは、従来の交流から直流への変換を最小化し、電力効率を劇的に高める取り組みです。特に、GPUが密集するAIサーバーでは、電源ユニットの小型化や銅の使用削減、高効率化が求められており、800Vの高電圧直流がその鍵になります。
この動きには、インフィニオンやTIなどのパワー半導体企業も連携し、SiC(シリコンカーバイド)やGaN(ガリウムナイトライド)といった次世代パワーデバイスの活用も進展しています。一方で、日本では高圧扱いとなるため、法規制や点検義務など運用面での課題も存在しますが、AI特化型データセンターの広がりとともにHVDCの採用が本格化する可能性があります。
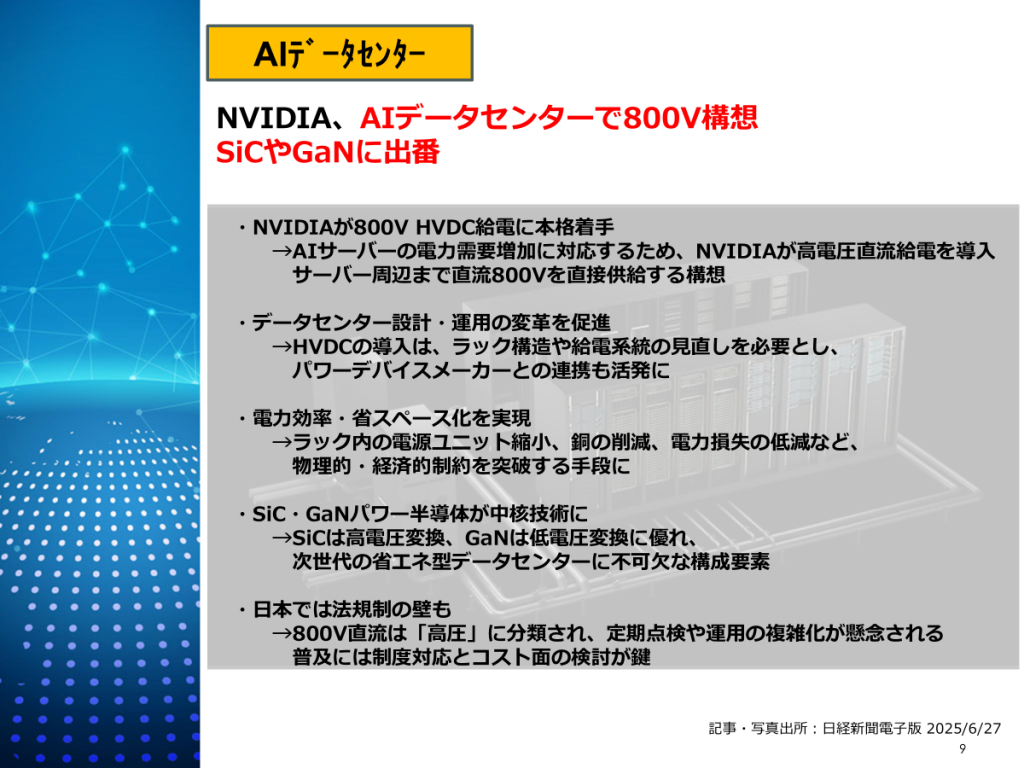
07:21 量子コンピューター専用データセンターの整備が進む
続いては量子コンピューターの進展に伴うデータセンターインフラの進化について、上下2本の記事をまとめてお伝えします。
量子コンピューターは、従来では解けなかった複雑な問題にアプローチできる技術ですが、その実用化には極低温・電磁波遮蔽といった特殊な環境が必要です。こうした背景から、量子コンピューター専用の次世代データセンター、量子データセンターの整備が加速しています。
特に注目されているのが、クラウド型で量子計算リソースを提供するQCaaS(カース/Quantum Computing as a Service)です。これにより、多くの企業や研究機関が量子技術にアクセスできるようになります。
今後は、冷却設備やハイブリッド計算環境、高度な騒音・振動対策を備えた専用ファシリティーが鍵を握ります。すでにエクイニクスが英スタートアップのオックスフォード・クァンタム・サーキッツと協働し、商用サービスを始動しており、量子時代のデータセンターが現実のものとなりつつあります。
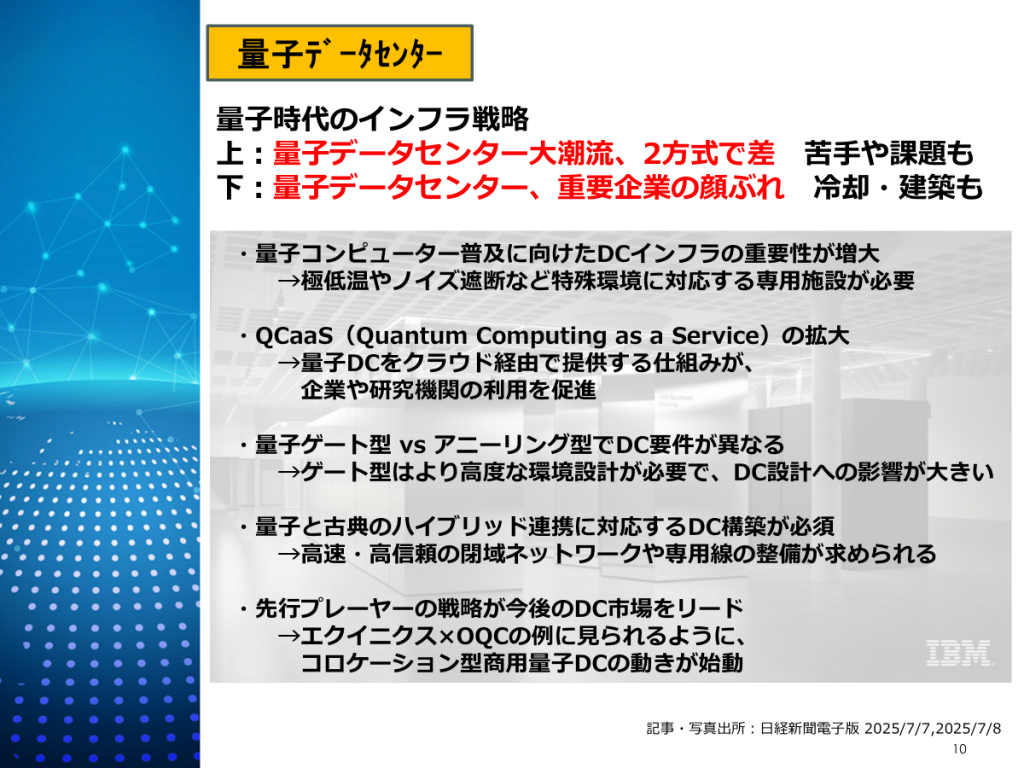
08:09 富士通「富岳NEXT」でAI向けスパコンへ
この新システムは、日本理化学研究所に設置される予定で、自社開発の次世代CPU「FUJITSU-MONAKA-X」を搭載。
注目すべきは、AI処理を高速化するために設計された低電力・高性能なマイクロアーキテクチャです。
この取り組みは、将来的にデータセンターのAI処理インフラに直結する技術として注目されており、ゼタスケール級の性能を目指すことで、日本が再びスーパーコンピューティングの世界リーダーになる可能性も。
また、富士通はこの技術をNPUなどのAIプロセッサにも展開し、AI需要の爆発的増加に備える強力な計算基盤の構築を目指しています。
つまり、富岳NEXTはただの研究用マシンではなく、次世代データセンター技術の先導役と言えます。
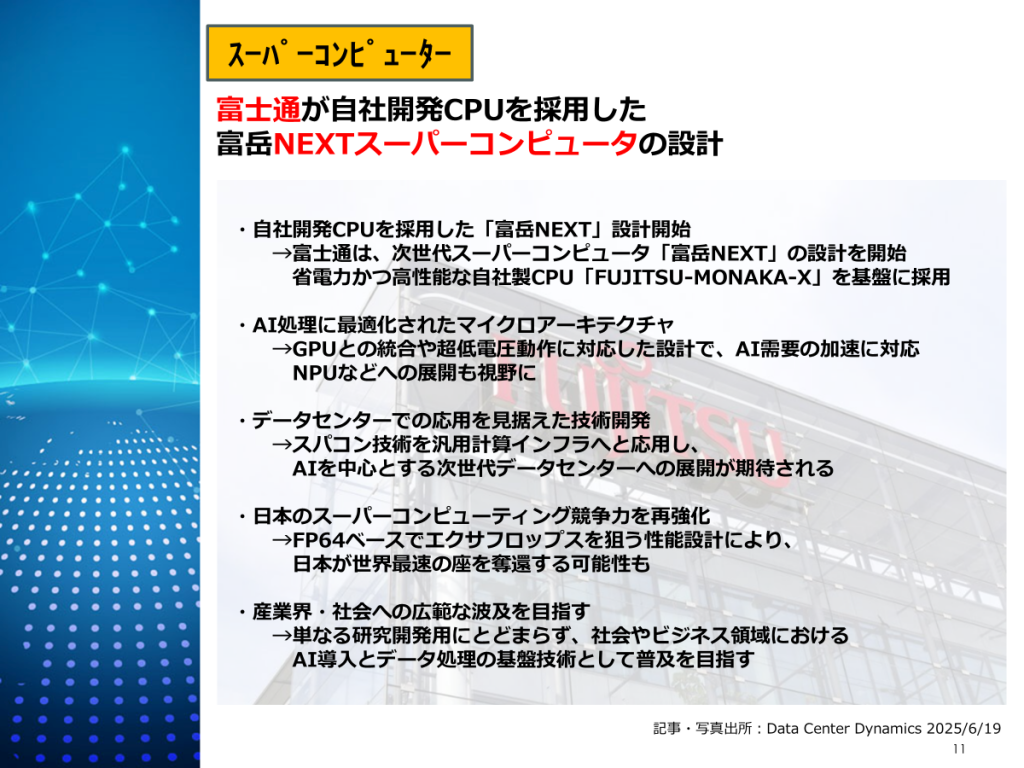
09:05 IBM × 理研が量子・古典ハイブリッド計算へ
最後に、理化学研究所がIBMと共同で、日本初となる「IBM Quantum System Two」の稼働を開始したという注目のニュースをお届けします。
この量子コンピューターは、理研のスーパーコンピューター「富岳」と同じ建物内に設置され、基礎的な命令レベルで接続されています。これにより、量子と古典の計算リソースを組み合わせた、次世代のハイブリッド型スーパーコンピューティングが実現可能となりました。
ポイントは、データセンターの中に量子コンピューターが組み込まれたこと。これにより、並列処理や低遅延通信といったHPCの世界において、量子の強みを活かした統合システムの実証が進みます。今後、量子計算とデータセンターの融合が進むことで、AIや材料開発などさまざまな分野に大きなブレイクスルーをもたらす可能性があります。
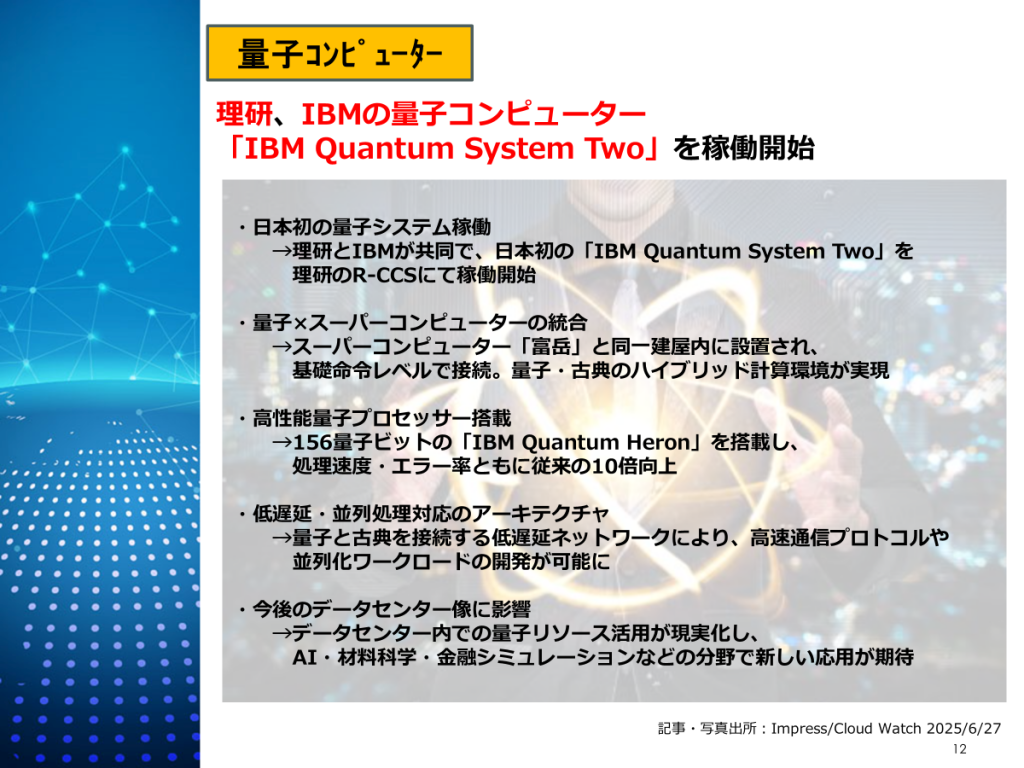
09:49 今月のまとめと雑感(コンビニがデータセンター⁉︎)
今月の記事をまとめますと、電力問題はいよいよ国際的な枠組みで課題解決を図っていくフェーズに入ってきました。まずG7が技術革新で協調を開始しましたが、こうした動きは今後も加速していくのではないでしょうか。また、企業レベルでは、将来的な電力確保にむけて次世代技術を活用する動きが始まっています。
電力問題解決のカギを握る光電融合技術では、先行するプレーヤーが限られてきましたが、日本勢も巻き返しを図っています。
電力問題の火付け役となったAIですが、AIデータセンターでは日本と海外では異なるアプローチを取り始めたように感じます。また、量子コンピューター専用のデータセンターの整備が加速しており、AI×量子、量子×スーパーコンピューターへの地盤固めが始まっています。
個人的にはKDDIがローソンをデータセンターとして活用する構想が面白かったです。 データセンターはコンビニから宇宙まで、海中から洋上まで、どこにでもいる存在としてますます進化していきそうですね!